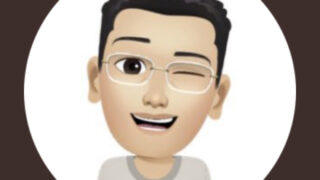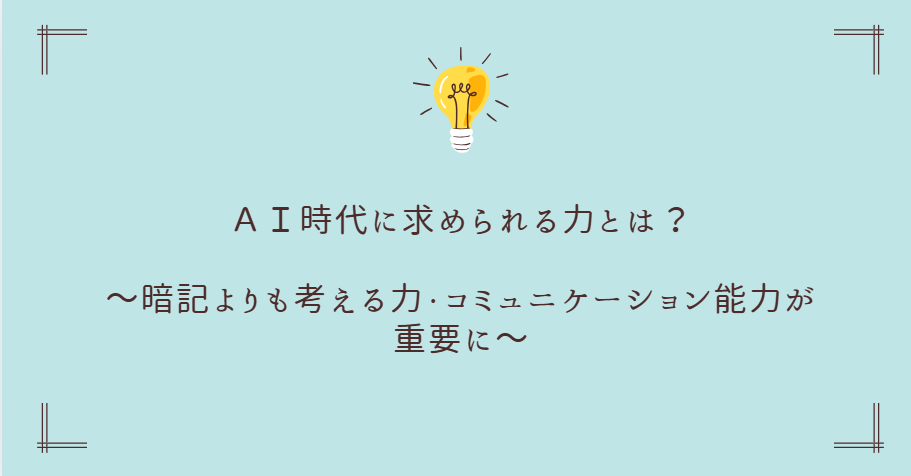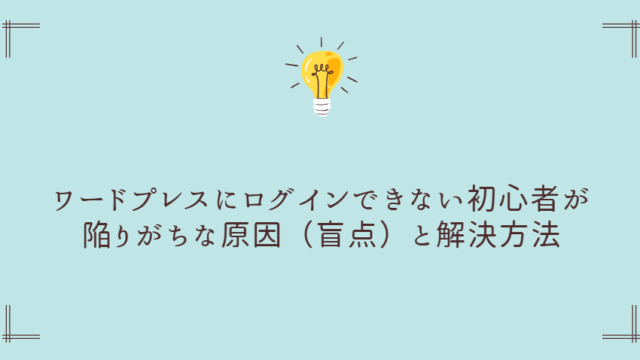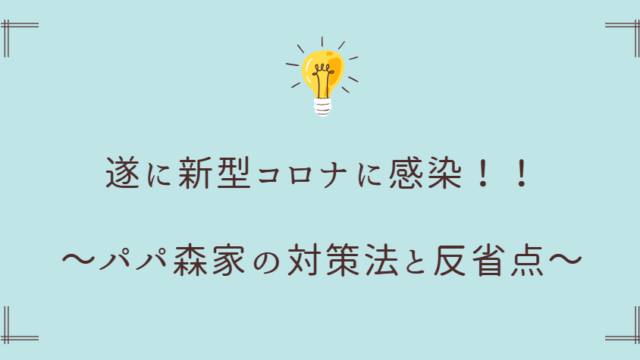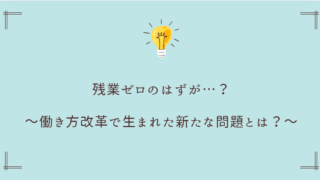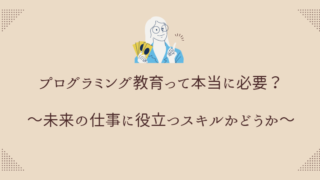お気に入り登録
お気に入り登録
AIの進化によって、仕事のあり方が大きく変わりつつあります。「これからの時代、どんなスキルを身につければいいのか?」と不安を感じる方も多いでしょう。実は、AI時代に活躍するためには、「人間にしかできないこと」を伸ばすことがカギとなります。今回の記事では、「AIが得意なこと・苦手なこと」「これからの時代に必要な3つの力」「子どもが将来AIと共存するために親ができること」について詳しく解説していきます。
AIが得意なこと・苦手なこと
昨今、AIの進化には著しいものがありますが、AIにも得意なことと、苦手なことがあります。まずは、その点について触れていきたいと思います。
1 AIが得意なこと(機械に任せられる仕事)
AIは、大量のデータを高速で処理し、正確な答えを導き出すことが得意です。
✅ データの処理・計算のスピードが速い
→ 例:「大量の顧客データを分析し、最適なマーケティング戦略を導く」
✅ 暗記・検索が得意
→ 例:「医療分野で過去の症例データをもとに病気を診断する」
✅ 単純作業の自動化ができる
→ 例:「工場のライン作業や、事務作業の自動化」
2 AIが苦手なこと(人間にしかできない仕事)
一方で、AIは創造性や人間らしい感情を持つことができません。
❌ ゼロから新しいアイデアを生み出すことが苦手
→ 例:「芸術作品を作る」「ビジネスの新しいコンセプトを考える」
❌ 人の感情を理解して適切に対応するのが難しい
→ 例:「相手の気持ちを汲み取って、励ます」「交渉や接客で相手に寄り添う」
❌ 倫理的判断や価値観を持つことができない
→ 例:「法律やモラルに基づいた正しい判断をする」
AI時代に求められる3つの力
AIが発達することで「機械にできる仕事」と「人間にしかできない仕事」が明確になってきています。これからの時代に求められるのは、AIを活用しながらも、人間ならではの強みを活かす力です。
1 考える力(思考力・創造力)
・「なぜ?」を考え、自分の頭で答えを導く力が求められます。
例:「AIが出した答えをそのまま受け入れるのではなく、本当に正しいのか批判的に考える」
・創造力 → AIが模倣はできても、ゼロから新しいものを生み出すのは人間の役割。→ 暗記ではなく、「考える経験」を増やしましょう。
2 コミュニケーション能力(対話・共感力)
・人の気持ちを理解し、適切な言葉で伝える力が求められます。
例:「上司や同僚と協力しながら仕事を進める」「顧客の本音を引き出し、最適な提案をする」
・交渉力・プレゼン力 → AIにはできない「人の心を動かす」スキルが求められます。→ 人と関わる機会を増やし、「相手を理解する力」を伸ばしましょう。
3 問題解決能力(課題を見つけ、解決する力)
・「何が問題なのか?」を発見する力が重要です。
・AIは決められた問題を解くのは得意ですが、「どんな問題を解くべきか」を考えることはできません。
例:「社会課題を解決する新しいビジネスを考える」「顧客が求める新しいサービスを開発する」→ 答えがない問題に挑戦する経験を積みましょう。
AI時代を生き抜くために親ができること
AI時代を生き抜くために親としてできることは、どのようなことがあるのでしょうか。
1 暗記ではなく「考える経験」を増やす
子どもに「なぜ?」と問いかけたり、間違いを恐れずに考える習慣をつけるようにしましょう。
2 人との関わりを大切にする
家庭内での会話を増やしたり、グループ活動に参加させたり(習い事・クラブ活動など)、発表やプレゼンの機会を作りましょう。
3 答えのない課題にチャレンジさせる
自由研究や探究学習を取り入れたり、社会の問題について考えさせたり(ニュースを一緒に見て議論する)、創造的な遊び(LEGO、プログラミング、アート)を取り入れましょう。
まとめ
AI時代に生きる子どもに必要な力とは、「考える力」「創造力」「論理的思考」「批判的思考」「コミュニケーション能力」「共感力」「プレゼン力」「チームワーク」「問題解決能力」「課題を見つけ、自ら解決する力」などが考えられます。
・AIは暗記や計算は得意ですが、「考えること」「共感すること」「創造すること」はできません。
・これからの時代は、思考力・コミュニケーション力・問題解決力がより重要になります。
・親としては、子どもが「考え、対話し、挑戦できる環境」を作ることが大切です。
AIが進化する時代だからこそ、「人にしかできない力」を伸ばすことが、未来を生き抜くカギになります。今からできることを、少しずつ取り入れていきましょう。
パパ森のブログをもっと見たいかたはこちらから

では、今回はここまでにしたいと思います。
また次の記事でお会いしましょう。
この記事を書いた人
この記事を書いたパパ森について、簡単に紹介させてください。