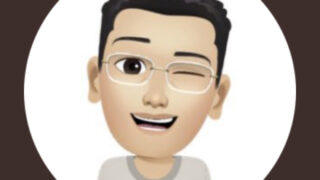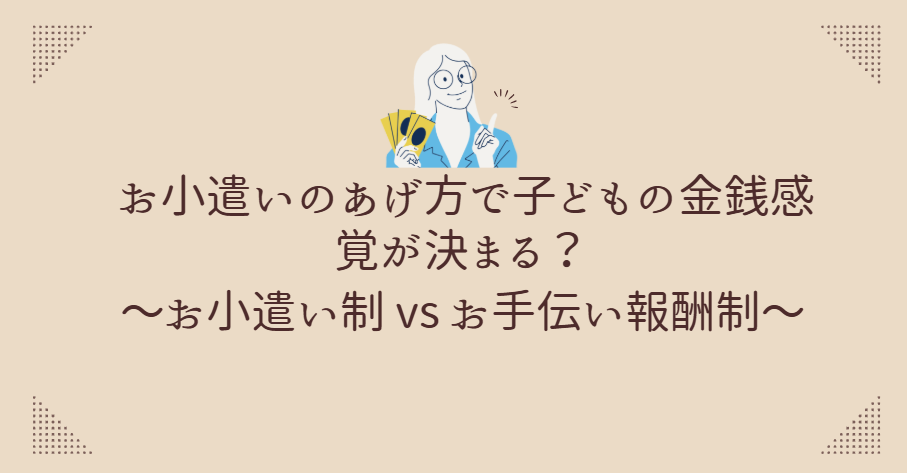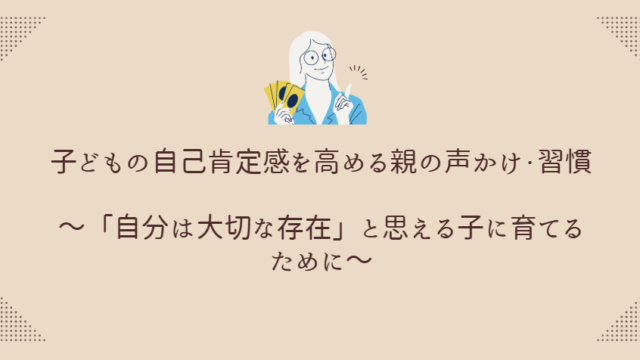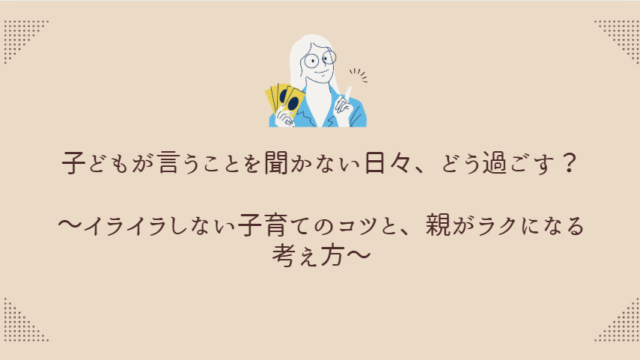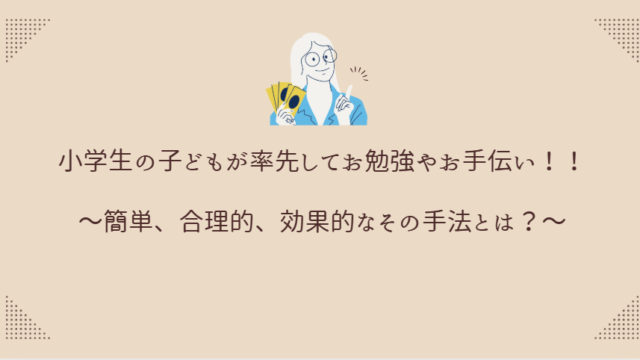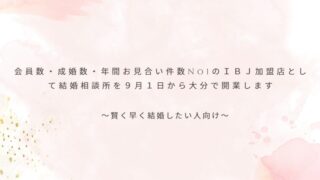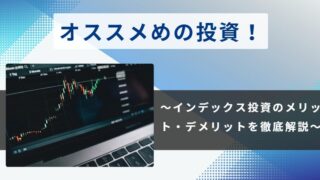お気に入り登録
お気に入り登録
「子どもにお小遣いをどうやってあげるのがいいの?」「毎月決まった額を渡すのがいい?それともお手伝いの報酬として渡すべき?」子どもの金銭感覚は、家庭でのお金の教育が大きく影響します。そのため、お小遣いのあげ方ひとつで、「お金の大切さ」や「管理能力」 が変わってくるのです。今回の記事では、「お小遣い制とお手伝い報酬制の違い」や「それぞれのメリット・デメリット」「どちらが子どもの金銭感覚を育てるのか?」といった内容について詳しく解説していきます。
お小遣い制 vs お手伝い報酬制 〜どんな方法?〜
まずは、「お小遣い制」と「お手伝い報酬制」のそれぞれの特徴を見てみましょう。
お小遣い制(定額制)
お小遣い制(定額制)とは、毎月・毎週決まった額を渡す方法です。
・小学生:月500〜1,000円
・中学生:月2,000〜3,000円
・高校生:月5,000〜10,000円
お手伝い報酬制(成果報酬制)
お手伝い報酬制(成果報酬制)とは、家の手伝いをしたら報酬を渡す方法です。
・ゴミ出し → 50円
・お皿洗い → 100円
・掃除機かけ → 200円
それぞれのメリット・デメリットは?
では、「お小遣い制」と「お手伝い報酬制」のメリット・デメリットについてそれぞれ述べます。
お小遣い制のメリット・デメリット
✔ 計画的にお金を管理する力が身に付きます。
✔ 「今月は〇〇に使おう」と考えられるようになります。
✔ 家庭の収入に関係なく、一定額を渡せます。
✖ 「もらうのが当たり前」になりがちになります。
✖ お金を稼ぐ大変さが実感しにくいです。
お手伝い報酬制のメリット・デメリット
✔ 働くことでお金を得る大切さが学べます。
✔ 「努力すれば報酬がもらえる」経験になります。
✔ 欲しいものがあるときに、積極的にお手伝いするようになります。
✖ お金がもらえないと手伝わなくなる可能性があります。
✖ 家事を「自分の仕事」として考えにくくなります。
どっちが子どもの金銭感覚を育てるのにいい?
実は、どちらか一方だけではなく、両方を組み合わせるのが理想的です。
✅ 基本は「お小遣い制」にして、お金の管理能力を養いましょう。
✅ 追加で「お手伝い報酬制」を取り入れ、働くことの大切さを学ばせましょう。
実践例!効果的なお小遣いのルール
実際に、お小遣いをうまく活用するために、以下のようなルールを決めておくと効果的です。
ルール① お小遣い帳をつけさせる!
お金の使い道を記録し、管理能力を育てましょう。
【例】
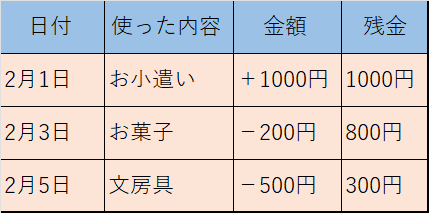
ルール② 「貯金用」と「使う用」に分ける!
お金を計画的に使う習慣をつけさせましょう。
・お小遣い1,000円のうち700円は自由に使う、300円は貯金する。
・欲しいものがあるときは、貯金を増やしていく。
ルール③ 「お手伝い報酬」は特別な仕事に限定する!
基本の家事は、家族の一員として手伝うことが前提としておきましょう。
⭕ 「特別な手伝い」に限って報酬を設定する。
✔ 庭の草むしり(1時間)→ 500円
✔ 祖父母の買い物を手伝う → 300円
❌ 「日常の家事」にはお金を払わない。
✖ お皿洗い → 無報酬(家族としての役割と認識してもらう。)
まとめ
お金の教育は、「お小遣い制」と「お手伝い報酬制」とのバランスが大事です。
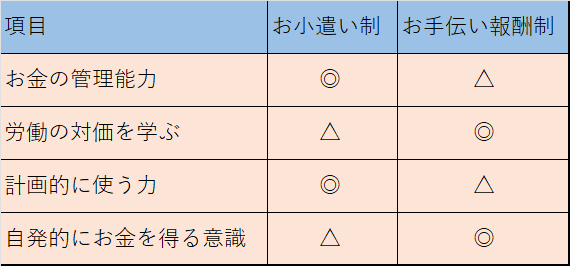
基本は、「お小遣い制」で「計画的に使う力」を養いつつ、特別なお手伝いには「報酬制」を取り入れ、「働く大切さ」を学ばせるのがよいでしょう。「お金の管理 × 労働の対価」の両方を学べる環境を作りましょう。
「お小遣いをどうするか?」は、子どもの将来の金銭感覚を育てる大事なポイントです。お子さんに合った方法を取り入れ、楽しみながらお金の教育をしていきましょう!
パパ森のブログをもっと見たいかたはこちらから

では、今回はここまでにしたいと思います。
また次の記事でお会いしましょう。
この記事を書いた人
この記事を書いたパパ森について、簡単に紹介させてください。