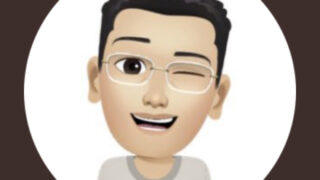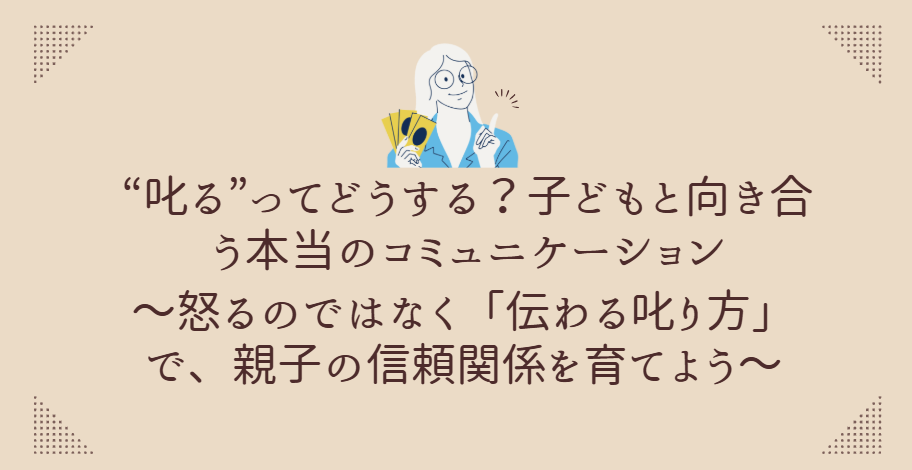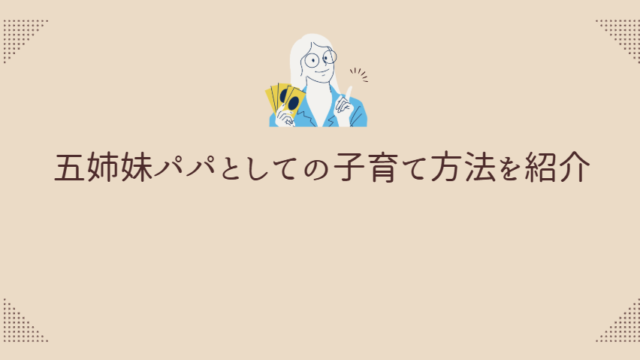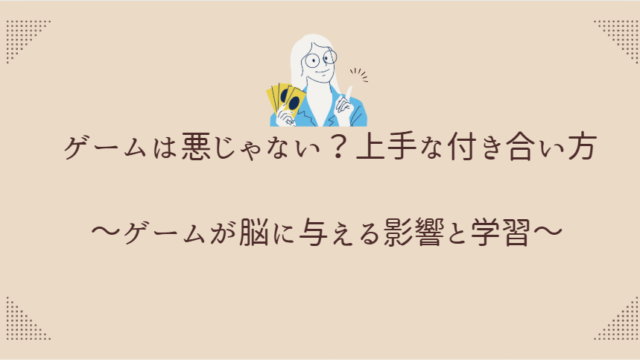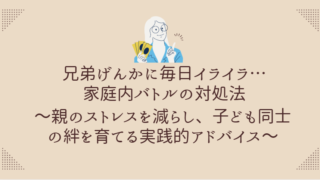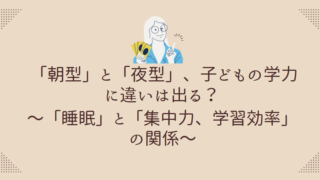お気に入り登録
お気に入り登録
子育てをしていると必ず直面するのが「叱り方」の悩みです。「つい感情的に怒ってしまう…」「叱ったつもりが、全然伝わっていない」「叱ると子どもの反発が強くなってしまう」こんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか。そもそも、「叱る」とは一体何のためにするのでしょう?それは「子どもが社会で生きていく上で必要なことを伝えるため」。
つまり、叱る目的は「子どもを傷つけること」でも「親の気持ちをぶつけること」でもありません。ですが、怒りの感情が先に立ってしまうと、つい「感情の爆発」=「怒る」になりがちです。叱ることは本来、子どもと「より良く生きるためのルール」を一緒に確認し、伝えていく作業です。ここを間違えると、親も子も疲れ果て、叱ることが苦痛な時間になってしまいます。今回の記事では、そんな「叱ること」の本当の意味と、今日からすぐ実践できる「伝わる叱り方」のコツを、具体的に解説していきます。「叱る」ことへの不安やストレスが軽くなり、親子の信頼関係がもっと深まるヒントになれば嬉しいです。
「怒る」と「叱る」はまったく違うもの
まず整理しておきたいのが、「怒る」と「叱る」の違いです。
• 怒る=感情をぶつけること。親の気持ちを吐き出すこと。
• 叱る=相手に「してはいけない理由」を伝え、理解を促すこと。
たとえば、食事中に遊び始めた子に対して――
✕「もう!ふざけないで食べなさい!!(怒る)」
〇「食事中に遊ぶとお腹いっぱいにならないし、食事が終わらなくなるよ。(叱る)」
伝わり方がまったく違います。
前者は、親のイライラ感情をぶつけただけ。後者は、「なぜその行動が良くないか」「どうすればいいか」を子どもが考えられる伝え方です。
子どもはまだ未熟。大人が伝えないと、「何がよくて何がダメか」は分かりません。だからこそ、叱るときは「感情」ではなく「伝えたい内容を意識する」ことが大事なのです。
叱るときにやってしまいがちなNGパターン
意識していても、つい無意識でやってしまいがちな「逆効果な叱り方」もあります。いくつか典型例を紹介します。
1 人格否定になっている
「なんであなたはいつもそうなの!」「ほんとダメな子ね」
これは行動ではなく「子どもそのものを否定する言葉」です。これが続くと、子どもは「自分はダメな人間だ」と自己否定感を持ちやすくなります。
×「いつもダメ」→〇「今のこれだけは良くない」
行動だけにフォーカスして伝えるのがポイントです。
2 理屈が多すぎる
「それはね、社会ではこうだから…」「昔からこうで…」と長々説明すると、子どもは話を聞かず、頭の中が「シャットアウト状態」になります。
特に小さい子ほど「具体的」「短く」「わかりやすく」が鉄則です。
3 タイミングがズレている
「そういえばさっきのアレだけど…」と時間がたってから叱っても、子どもは「何のこと?」となりがちです。できれば行動直後に伝えましょう。「いま・ここ」の出来事に限定することで伝わりやすくなります。
「伝わる叱り方」5つのコツ
では、どうすれば子どもに届く「叱り方」ができるのでしょうか。すぐに実践できるコツを5つご紹介します。
1 「○○しないで」より「○○してほしい」と伝える
×「走っちゃダメ」→〇「歩いてね」
×「ふざけないで」→〇「静かに聞いてくれる?」
否定形よりも、「やってほしい行動」を具体的に伝える方が子どもには理解しやすいのです。
2 「今の行動」にだけフォーカスする
「またやった」「いつもこう」など、過去の失敗や癖を引っ張り出すと、子どもはうんざりします。
あくまで“今”の行動にだけ焦点を当てると、納得しやすくなります。
3 感情はできるだけ冷静に
イライラしたら、まず深呼吸です。怒りのピークは6秒と言われます。6秒数えてから伝えるだけで、言葉がぐっと変わります。「怒りをぶつけるために叱るのではなく、伝えるために叱る」――その意識を持つだけでも効果絶大です。
4 理由を端的に伝える
「なぜダメなのか」「どうしてそれが必要なのか」を短く説明すると、子どもの理解が進みます。
「お店で走ると他の人にぶつかって危ないから、歩こうね」
「理由づけ」は子どもの「納得感」を生む大切な要素です。
5 「できたらほめる」までワンセット
叱るだけだと気持ちは沈んでしまいます。叱った後は、「できたね」「よく直せたね」と必ず声をかけると、子どもは「また頑張ろう」と思えます。
叱る→改善→ほめる
この流れを意識すると、子どもも前向きになります。
「叱ること」=「親が成長する機会」
実は、「叱る」という行為そのものが、親自身にとっても成長のチャンスになります。
なぜなら――
• 自分の感情コントロールを学べる
• 伝え方を工夫する力が育つ
• 子どもの気持ちをくみ取る想像力が磨かれる
子どもと向き合うことで、親もまた「育てられている」のです。
「私はまた感情的になっちゃった…」と思う日があっても大丈夫。その気づきこそ、成長の第一歩です。完璧な叱り方はないからこそ、日々試行錯誤しながら少しずつ“伝わる叱り方”を積み重ねればいいのです。
叱るときの「魔法のフレーズ」3選
最後に、明日からすぐ使える「叱るときに役立つ声かけ」を3つご紹介します。
1 「どうしたかったの?」
子どもの本音を聞き出す魔法の質問です。「~したかったけど失敗した」が出てくることもあります。
2 「次はどうしたらいいと思う?」
自分で考える力を育てます。叱るのではなく「一緒に考える」時間にしましょう。
3 「わかったよ。でもこうしてくれると嬉しいな」
共感+要望で、素直に聞きやすくなります。反発がぐっと減ることでしょう。
おわりに
「叱ること」は、親も子もイヤな気持ちになるもの――そう思われがちですが、
実は「親子の信頼関係を深めるチャンス」でもあります。
・感情ではなく「伝えたいこと」を意識する
・子どもの理解度に合わせた言葉を選ぶ
・叱った後に、ほめる・認める
この流れが身についてくると、叱ることへの不安がなくなり、親も子も前向きな気持ちになれます。
完璧な叱り方を目指す必要はありません。日々の小さな「伝わるコミュニケーション」の積み重ねこそ、子どもとの信頼を築いていく最大のコツです。
今日のあなたの「ひと言」が、子どもにとって一生の宝物になるかもしれません。どうか、自分自身の育ちも楽しみながら、子どもと一緒に歩んでいきましょう。
パパ森のブログをもっと見たいかたはこちらから

では、今回はここまでにしたいと思います。
また次の記事でお会いしましょう。
この記事を書いた人
この記事を書いたパパ森について、簡単に紹介させてください。