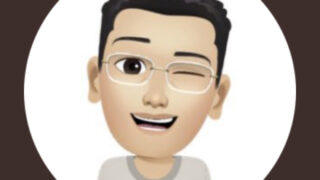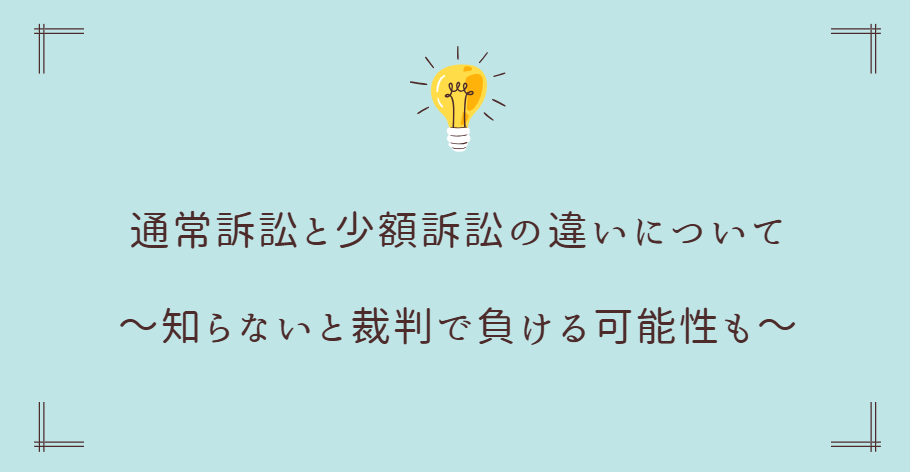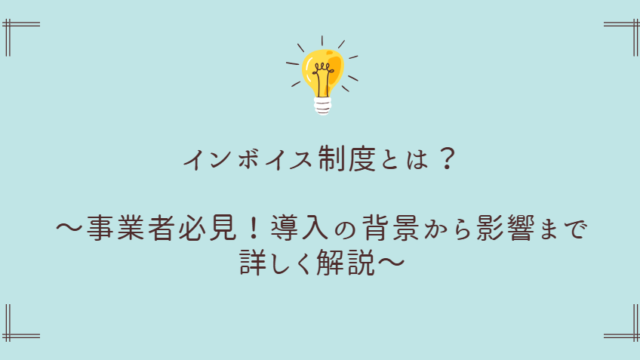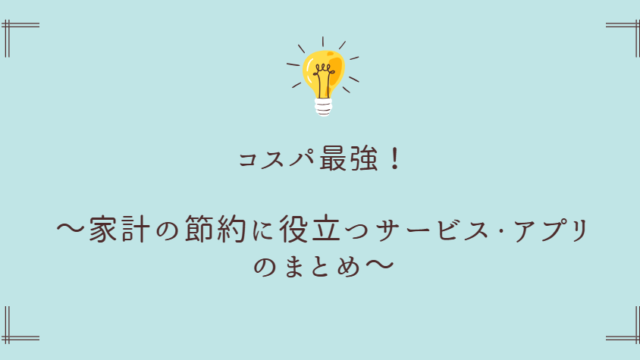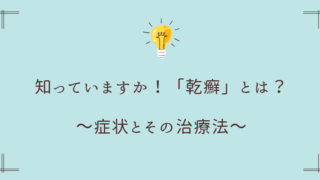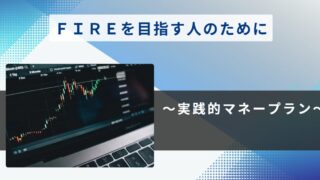お気に入り登録
お気に入り登録
金銭トラブルに巻き込まれた場合、「弁護士に相談する」「裁判所に裁判を訴訟提起する」などが考えられますが、弁護士に相談した場合、請求金額が小さいと、弁護士費用が賄えなくなるので、「少額訴訟」をすすめられるケースが多いようです。でも、少額訴訟の手続の特徴を知らないと「そんなこと知らなかった」「勝てる裁判に負けてしまった」と、後で後悔するケースも多いので、ここで注意喚起も兼ねて、「通常訴訟」と「少額訴訟」の手続きの違いについてご紹介します。
通常訴訟と少額訴訟の違い(概要)
一般的に、通常訴訟は請求金額に応じて、訴訟提起する裁判所が異なってきます。少額訴訟は簡易裁判所にしか訴訟提起できないので、まずは、そこを押さえておきましょう。
請求金額が140万円まで→簡易裁判所へ訴訟提起
請求金額が140万円を超える→地方裁判所へ訴訟提起
請求金額が60万円まで→簡易裁判所
通常訴訟の特徴
通常訴訟は、以下のような流れで進んでいきます。手続の途中で、お互いが判決を求めるのではなく、話合いで解決したいと考えた場合は、「和解」という手続で、お互いが譲歩し合って、解決する方法を選ぶこともできます。
訴訟提起
訴状、証拠の写し、証拠説明書(必要に応じて)、これらの副本、申立手数料及び指定された郵便切手を添えて裁判所に提出します。裁判所が、訴状を受け付けたら、「事件番号」が付されます。
訴状審査
裁判所は、受付係で、「受付・立件」後、「記録を編成」し、記録は、立会係(実際に裁判を行う係)へ引き継がれ、立会係は、「訴状審査」をしたうえで、「仮に被告が応答しなかった場合に、原告の主張を認めることができるか」(法的な要件の記載が整っているか)を審査します。
期日指定
上記審査をクリアすれば、裁判所は、実際の「裁判の期日」を指定します。概ね、訴状審査クリア後、1か月~1か月半先頃に指定されるのが一般的です。
裁判の期日が指定された場合、原告には、裁判の日時場所を知らせる文書が、原則「特別送達」という方法で知らされます。被告には、訴状副本一式が送られるほか、裁判の日時場所が知らされるとともに「答弁書」を提出してくださいという案内が送付されます。
答弁書の提出
被告は、裁判所から呼出し状及び訴状一式を受け取った場合、原則として答弁書を裁判期日の1週間前までに裁判所に提出するよう求められます。訴状には、原告の言い分しか書いてないので、その訴状の中身について、被告に間違いがないかを確認するために、答弁を求めるのです。
裁判期日
被告が、答弁書を提出したり、答弁書を提出しなくても裁判期日に出頭した場合は、裁判所は、公開の法廷の場で、双方からの言い分を聞くことになります。ここでは、実際に、原告と被告が法廷に集い、お互いの「主張」を言い合ったり、証拠を出し合って「立証」し合ったりして裁判を進めていきます。
主張段階
お互いの言い分を言い合うことを「主張」と言いますが、まずは、この主張を原告及び被告間でおこないます。
第1階口頭弁論期日
初回の口頭弁論期日は、まず「訴状陳述」から始まります。この訴状陳述とは、「訴状記載のとおり法廷で述べます。」という意味です。本来は、法廷で訴状を全て読み上げないといけないのですが、そんなことしてたら時間がかかるし、あらかじめ裁判官も被告も訴状に目を通しているので、「訴状のとおり陳述します」と言うだけで、訴状の内容をすべて法廷で言ったこととみなされるのです。
その後、被告が答弁書を提出している場合は、「答弁書陳述」し、答弁書を提出していない場合は、直接その場で、裁判官が被告に対して、答弁を求めます。
裁判期日の続行
お互いの言い分が異なる場合は、どこに争いがあるのか(争点)について、裁判官が指揮をとって裁判を進めます。概ね1期日あたり30分程度の枠が設けられていますが、時間が足りない場合は、次回期日が指定されるとともに、当事者に次回期日までに準備すべき事項としての「宿題」が課されます。
立証段階
お互いの言い分(主張)が出尽くしたら、争点が整理され、その争点について裁判官が判断するための手続きとして、「証拠調べ」(立証)が行われます。この立証の方法としては、大きく2つに分かれます。
書面による証拠調べ
貸金請求事件を例にした場合、例えば、貸したこと自体が争点になった場合は、原告側で貸したことを立証する必要があります。この場合、一番に考えられる証拠書面としては、「金銭借用証書」です。金銭借用証書は有力な証拠ですが、被告が、「金銭借用書の氏名欄は自分で書いたものではなく、第三者が書いたものだ。」などと反論されたら、その部分について更に調べることが必要となってきます。その場合、「筆跡鑑定」などをする必要もあるかもしれません。
人による証拠調べ
上記の例で、「金銭借用証書」を作っていなくて、口頭で契約したなどの場合は、書面で立証することができないので、「原告本人」や「被告本人」又は経緯を知っている「証人」などを呼んで、実際の出来事について、裁判官や弁護士が付いている場合は弁護士などど質疑応答する形で立証していきます。
弁論終結
主張で争点を炙り出し、その争点についてお互い立証を尽くした段階で、裁判は終結を迎えます。これを「弁論終結」と言います。弁論が終結されると、次回期日で判決が言い渡されることになります。
判決
判決は、弁論終結から早い事案であれば1週間後、長くても1~3か月後には言い渡されます。この判決言渡の期日の出頭は任意ですが、出頭しない人がほとんどです。理由は、判決が言い渡されると、裁判所書記官が判決の正本(判決原本と同じ効力のある書面。これを「債務名義」と言います。)を原告及び被告にそれぞれ特別送達してお知らせしてくれるからです。
控訴
判決が出ると、裁判の勝ち負けが決まります。勝った方は嬉しいでしょうが、負けた方は不満が残ります。そこで、判決に対して不満がある場合は、「控訴」という手続きをとることができます。
控訴ができる期間は、判決を受け取った日の翌日から2週間以内です。この2週間の間に控訴をすると、もう一つ上の上級審で審理が続審されることになります。双方ともに控訴をしなければ、判決が確定し、その判決が「債務名義」となります。
少々説明が長くなりましたが、この通常訴訟と比べ、少額訴訟はどのような特徴があるのでしょうか。
民事訴訟法には、民事裁判の手続について規定がされていますが、少額訴訟は、その「民事裁判の特則」という位置づけで規定されています。
それでは、少額訴訟に関する特徴を見ていきましょう。
少額訴訟の特徴
基本的な手続の流れは、通常訴訟と同じなのですが、以下のとおりの違いがあり、そこを理解した上で、手続を選ぶ必要があります。
また、先で述べたとおり、少額訴訟は60万円までの金銭請求に限られ、不動産の明け渡しや所有権の移転登記請求などは、少額訴訟手続から除外されている点にも注意が必要です。
以下に、少額訴訟の特徴について述べます。
1 被告の同意が必要
少額訴訟手続は、原告が少額訴訟手続を望んだとしても、被告が少額訴訟手続で進めることにつき「同意」しなければ、通常訴訟に移行することになります。
また、事案が複雑だったりすると、裁判官の「職権」で、通常訴訟に移行することもあります。
2 訴訟提起には回数制限がある
少額訴訟手続は、年に「10回まで」という制限があります。が、そんなに申立てされる方はいません。しかも、そもそも、そんなに少額訴訟手続を利用する人も多くないので、法制度を制定したときの見込み違いがあったのかもしれませんね。
3 一期日審理の原則(証拠書類や証人は、その日に調べられるものに限られる。)
少額訴訟は、紛争額に見合った経済的負担で、迅速かつ効果的に紛争解決を図るという手続創設の趣旨から、原則1回の期日での終了を目指します。
4 即時判決の原則
少額訴訟は、1回で期日を終了するのが原則であるところ、弁論終結すると直ちに判決が言い渡されます。
5 控訴の禁止と異議申し立て
通常の裁判では、先に触れたとおり、不服があれば「控訴」ができますが、少額訴訟では、不服があっても控訴ができず、「異議申し立て」しかできません。
異議申立ては、判決書を受け取ってから2週間以内にしなければならず、適式な異議申し立てがあった場合は、判決の効力が遮断され、弁論終結前の状態に戻り、「同様の簡易裁判所」で、通常訴訟として審理及び裁判がなされます。
選ぶのはあなた
以上のように、通常訴訟と少額訴訟ではその手続きに大きな違いがあります。一概にどちがら良いとは言えませんが、これらの特徴をしっかり理解した上で、提起する必要があります。
今回は、「通常訴訟と少額訴訟の違いやその特徴」について触れましたが、意外と盲点となる特徴があるので、注意して手続きを選択してください。
パパ森のブログをもっと見たいかたはこちらから

では、今回はここまでにしたいと思います。
また次の記事でお会いしましょう。
この記事を書いた人
この記事を書いたパパ森について、簡単に紹介させてください。